これによく似た話が江戸時代の作家の井原西鶴の推理小説『本朝桜陰比事』にある。
今日はその物語を紹介したい。
昔、京の町で7歳の子供が誤って9歳の子を小刀で刺して死なせてしまう事故が起きた。
人を殺してしまった子供は奉行による裁きの受けることになったのだが、子供の家族はまだ思慮分別のない幼子のしたことなのでと寛大な措置を懇願し、被害者の遺族は厳罰に処すように強く訴える。
この時代の裁判官であるお奉行さまは人形と小判を取り出し、「その子が人形を選べば御咎め無し、小判を選べば分別がつくと判断して死罪とする。明日子供をここへ連れてくること」と宣言して一旦はお開きとなった。
子供の家族はその夜、お奉行さまが出した人形と同じ人形を入手し、その子供に人形と小判を見せて「小判を取ったら殺されるぞ」と何度も何度も同じことを何百遍も言い聞かせた。
果たしてあくる日、奉行から「小判を取れば死罪だぞ」と言われながら人形と小判を出された子供は家族の願いもむなしく小判を選んだ。
被害者の遺族は大喜び。よっしゃ死罪じゃとはしゃいでいる。
子供の家族は声を上げて泣いた。
しかし意外な判決が下される。
「子供は無罪とする。この子にまだ分別がないことがよく分かった。あれだけ小判を取れば死罪だと言ったのに小判を取ったのがその証だ。この子は死罪の意味すら分かっていないのだ」とお奉行さまは言ったとさ。
おそらく小判を取っても人形を取ってもお奉行さまは罪を問わないつもりだったのだろう。
どうだろう。グリム童話では何の救いもなかった話が、なんだかハートフルストーリーに変貌しているw西鶴すげえぜ!
ちなみにこの西鶴の連作小説に登場する奉行は、大岡越前に次ぐ名奉行として名高い京都所司代の板倉勝重と重宗の親子がモデルだそうである。
重宗については死刑囚に対して刑を延期にしてでも反論の機会を与えて慎重に取り調べ、言い分が全てなくなってから刑に処したなどの逸話が遺されている。
〈参考資料〉
フリー百科事典Wikipedia
〈関連記事〉
【グリム童話】子どもたちが屠殺ごっこをした話【削除された話】
スポンサードリンク
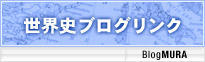
にほんブログ村
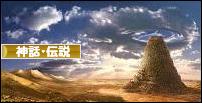
にほんブログ村
にほんブログ村



